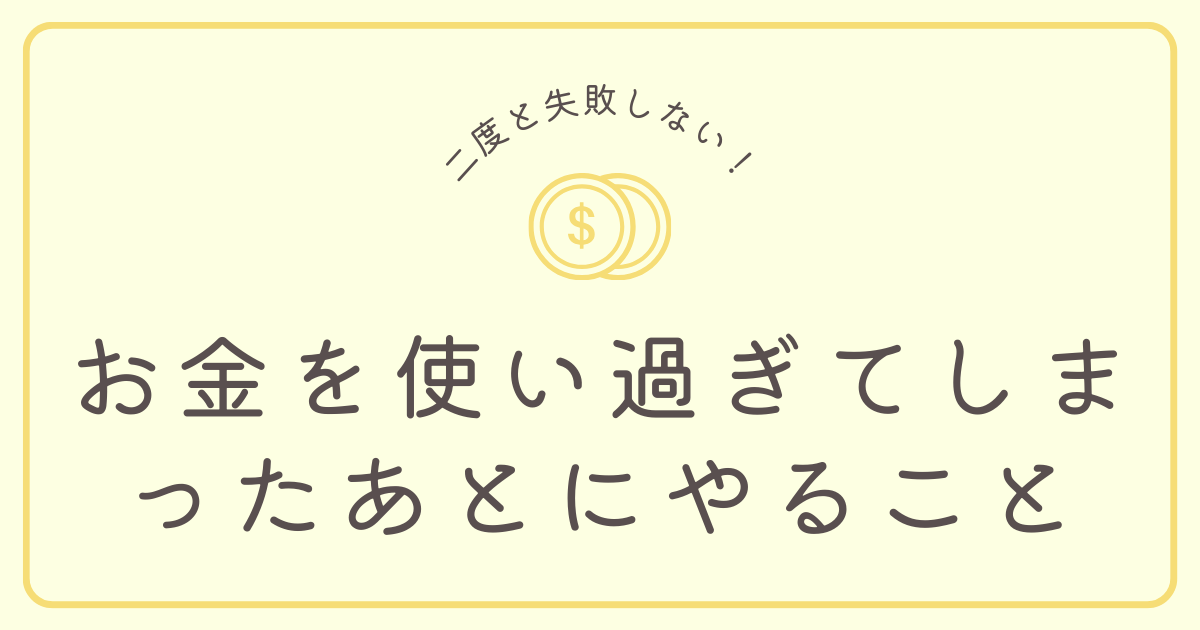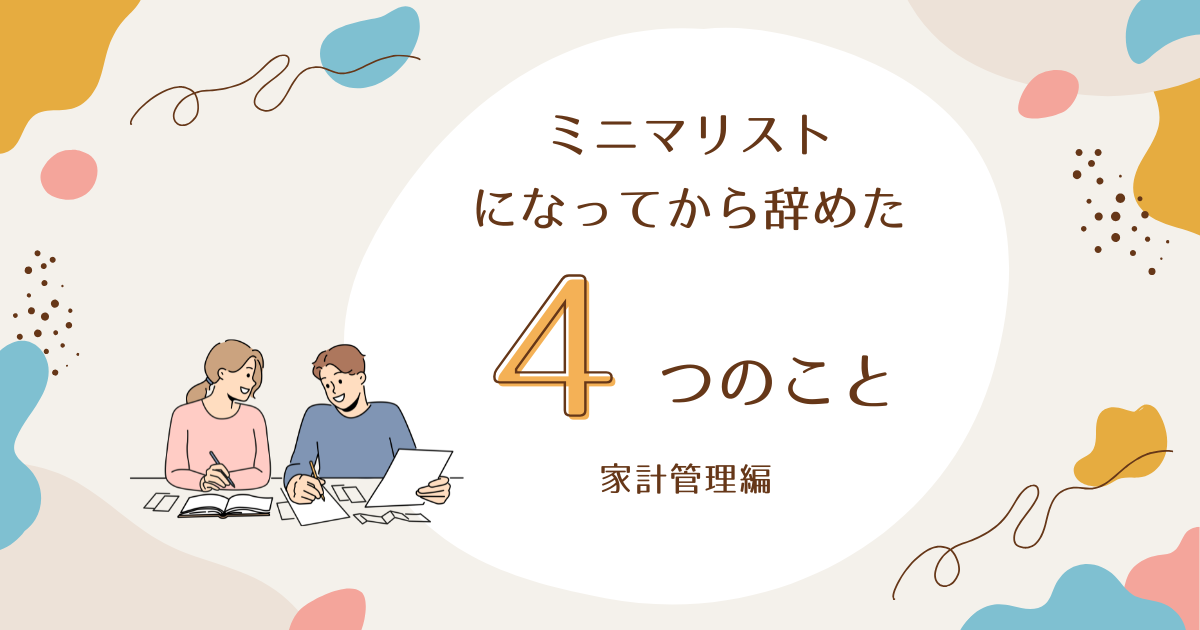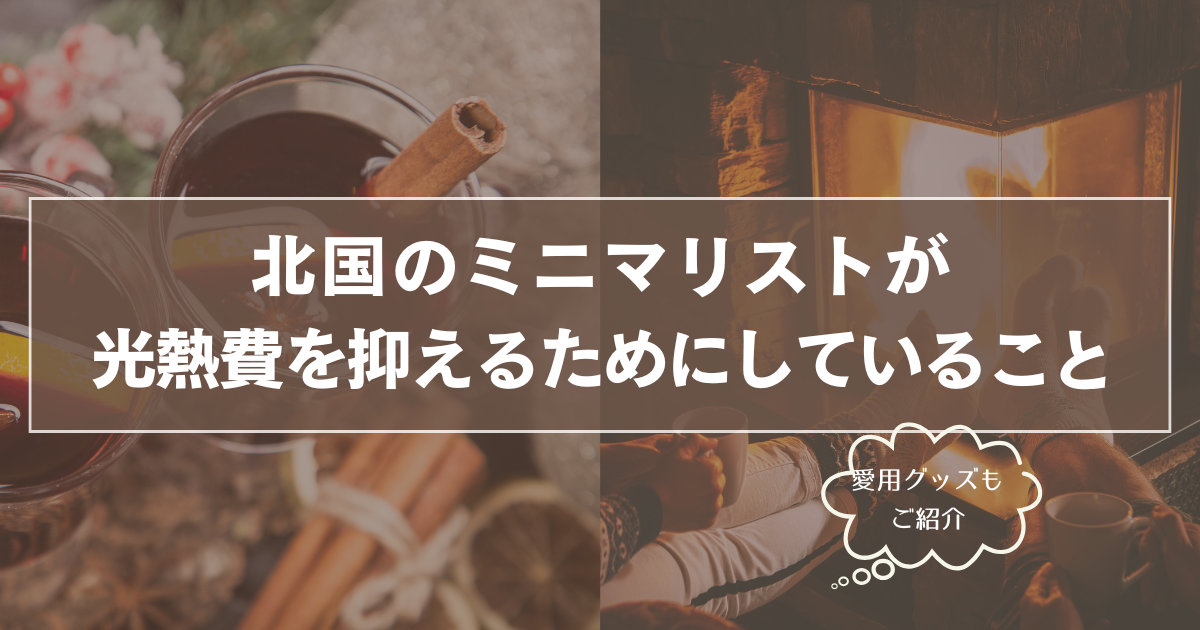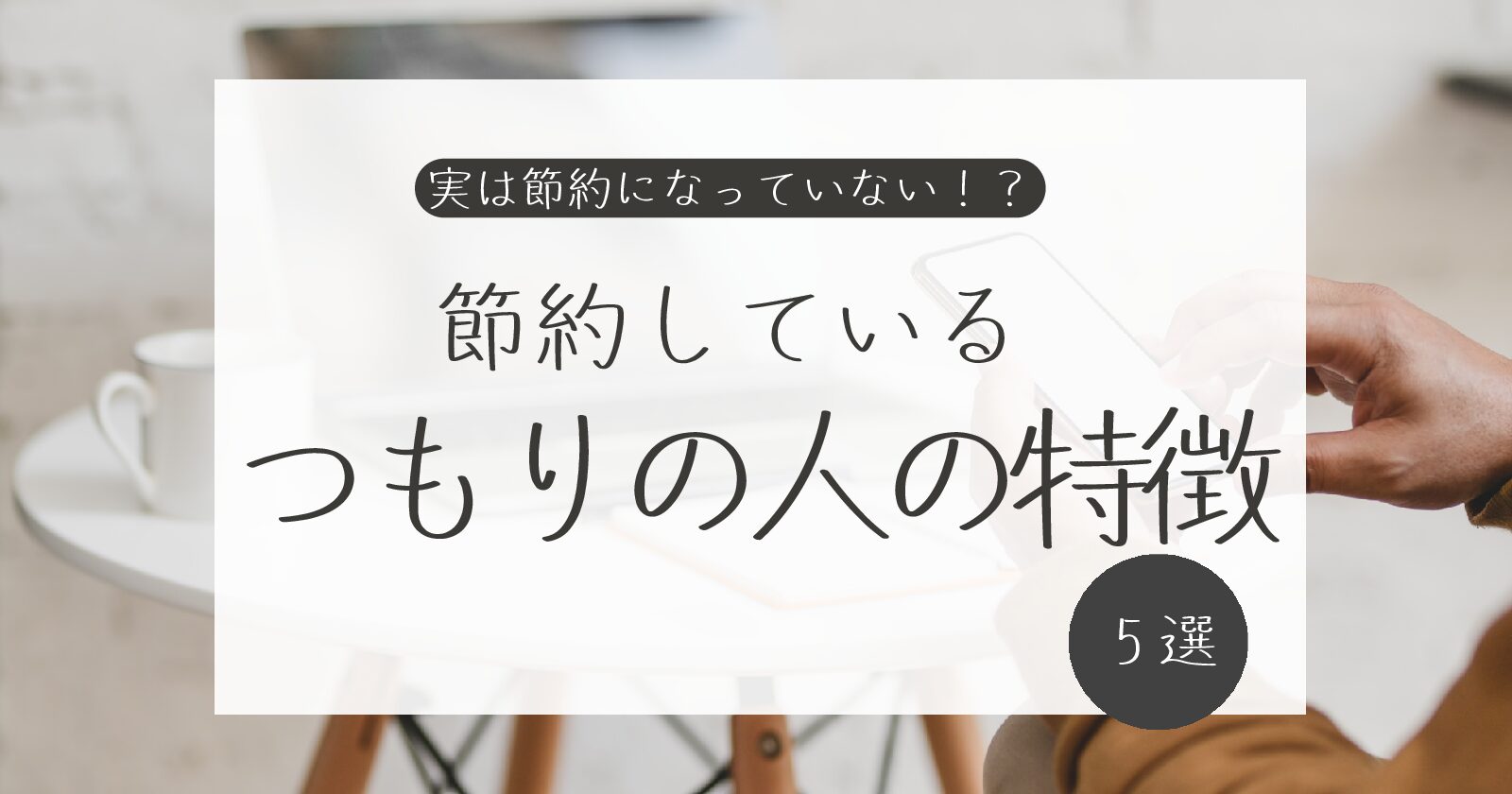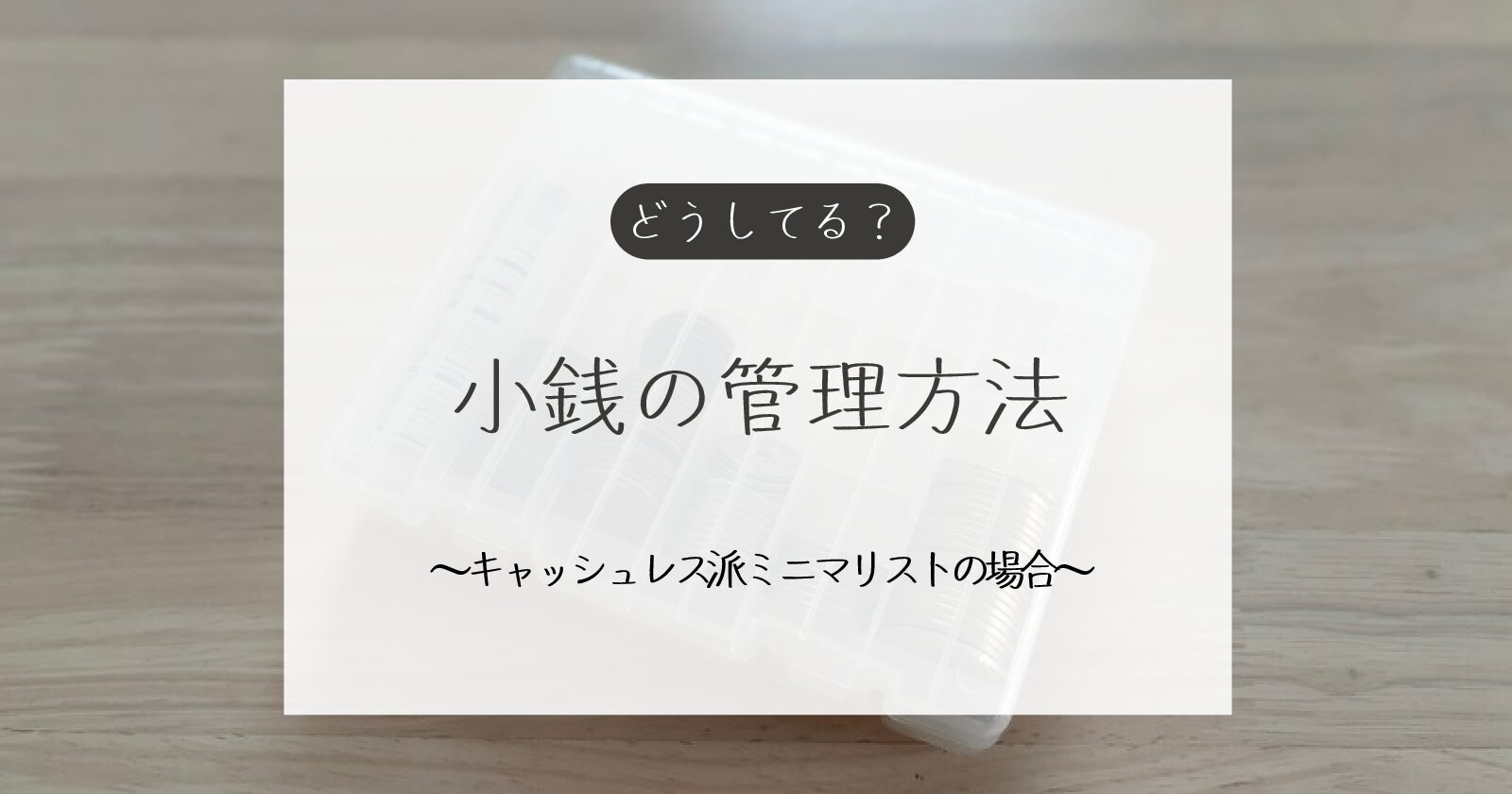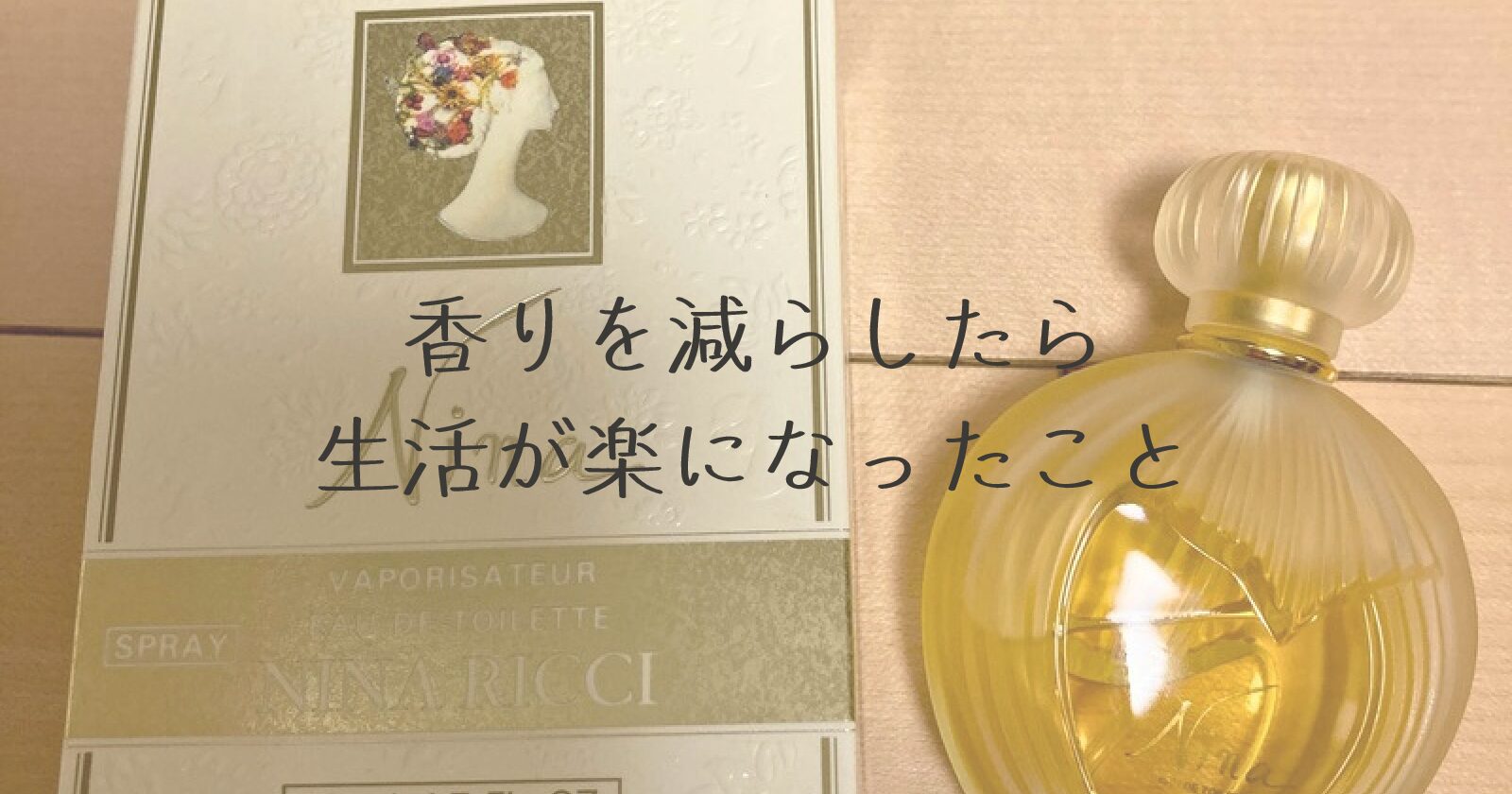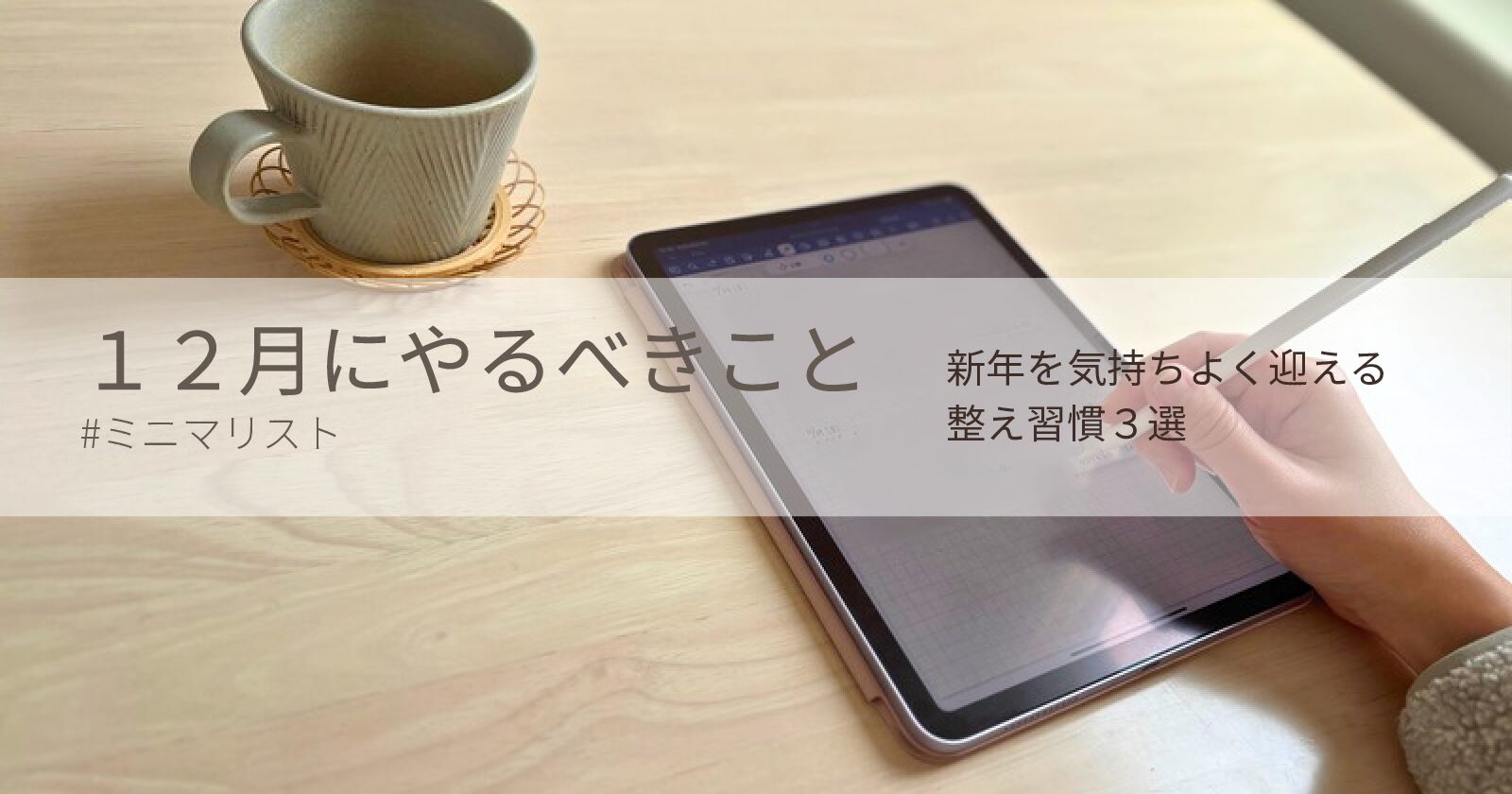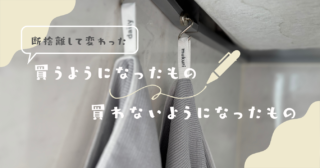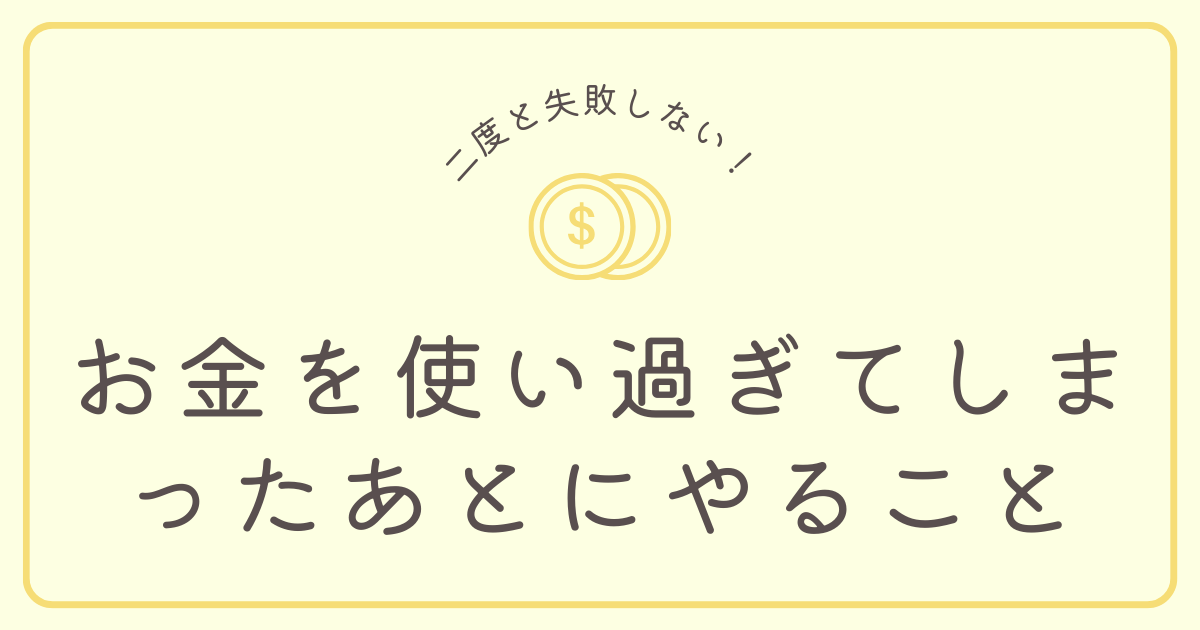
11月のブラックフライデーから始まり、クリスマス、忘年会、お正月と何かと出費が嵩みやすい年末年始。気を付けてはいたけど予算オーバーしてしまった!という人もいるのではないでしょうか。この記事では、二度とお金の使い過ぎにならないような対策をお伝えします。
1.お金の流れを「見える化」する
まずは何にいくらお金を使ったのか、全て書き出します。
金額を覚えていない場合は、1円単位で書き出す必要はなく、だいたい覚えている金額や範囲で構いません。ただし、少なく見積もりよりは少し多めに見積もるようにしましょう。
カードで支払いをしている人は、カード会社のホームページに行ってマイページにログインすると金額が確認できる場合があります(ネットショッピングも同じ)。
ここで大切なのは何にいくら使ったのか、支出を客観的に見つめ直すことです。
2.消費・浪費・投資に分類する
次に1で書き出した金額を「消費・浪費・投資」の3つに分類します。
この3つの違いをしっかりと抑えることで、今後の家計管理(資産形成)にも繋がります。
では、そもそも消費・浪費・投資の違いは何なのか意味を押さえましょう。
| 意味 | 心理的結果 | 例 | |
| 消費 | 必要なものへの支出 | 生活の維持・安定 | 食費、家賃、公共料金 |
| 浪費 | 不要・無駄な支出 | 後悔や一時的な満足感 | 衝動買い、高額な外食 |
| 投資 | 将来の利益や価値を得るための支出 | 成長・利益・価値の向上 | 資産運用、自己啓発、健康管理 |
たとえば、以下のように考えてみましょう。
消費の例
・食材や日用品の購入
・家賃や光熱費の支払い
これらは生活を維持するために必要な支出で、避けることが難しいものです。
ただし、「お得なセールで買う」「光熱費を節約する」などの工夫次第で金額を抑えることが可能です。
浪費の例
・流行に乗って買ったものの、ほとんど使わない高価な服
・頻繁に利用するカフェでの高額なドリンク
・衝動買いしたけれど後悔したアイテム
浪費は一時的な満足感を得ることができますが、後になって「使わなくてもよかったかな…」と思うことが多いです。
これを減らすことが支出を抑える第一歩。浪費との向かい合い方が上手な人は貯蓄上手な人です。
投資の例
・自己成長のための書籍やセミナー参加費
・資格取得やスキルアップのための講座料
・将来の健康のためのフィットネスジム利用料
投資は、短期的な満足感よりも、将来的な価値や利益につながる支出です。積極的に取り入れることで、長期的に家計や人生にプラスの影響を与えます。
ですが正直、浪費と投資の分類は難しいところです。
当時は投資だと思っていたけど、時間が経ってから振り返ると浪費だった、なんていうことは家計管理に慣れている人でもよくあります。
ここでは「将来的な価値や利益につながる支出」が投資という考えになるので、最初の例は以下のようになります。
・自己成長のための書籍やセミナー参加費→副業や収入UPに繋がる
・資格取得やスキルアップのための講座料→転職をして年収UPに繋がる
・将来の健康のためのフィットネスジム利用料→医療費の削減
3.共通項目を見つける
分類後、それぞれのカテゴリで共通する支出内容を探してみましょう。以下に例を示します。
・消費の共通点‥‥同じ商品やサービスに定期的に支出していないか?消費しきれない量を一度に買って、使いきれずに捨てていいないか?(例:毎日同じカフェでコーヒー購入)
・浪費の共通点…特定のシチュエーションで無駄遣いしていないか?投資だと思っていたのは本当に投資だったか?(例:ストレスが溜まったときの衝動買い)
・投資の共通点…自己成長や健康維持にどの程度お金を使っているか?投資だと言える根拠は何か?(例:月1回のセミナー参加費)
慣れるまで少し時間がかかるかもしれませんが、共通点を見つけることで改善点や見直すべき支出が明確になります。
4. 共通項目を改善する
共通項目を分析したら、次の買い物にどう繋げるかを考えましょう。
・消費の改善…カフェのコーヒーではなく、自分で家で淹れたコーヒーを持って行く
・浪費の抑制…ストレスを溜めないように運動を習慣化する
・投資の強化…将来の目標に繋がる支出を増やし、自己成長に繋がるアイテムやサービスを優先的に選ぶ。
支出を分類し続けると、自然と自分の改善すべき共通項目が見つかります。
5.もう二度とお金を使い過ぎないコツ
何が消費で何が浪費または投資かが分かったら、今度は無駄な支出を減らすような取り組みを行いましょう。
①予算を決める
無駄な消費を押さえるためには、まず何にいくら使うのか「予算を立てること」が重要になります。予算の中であれば、何にいくら使うのか自由です。それと同時に貯蓄もできるようになります。
それではどうやって予算を立てるのか、その手順をご紹介します。
(1)毎月の収入を把握する
当たり前ですが収入以上の支出があれば赤字(マイナス家計)です。ですので、毎月使える金額は全体でいくらなのか把握します。
(2)毎月かかる固定費を把握する
固定費とは、家賃、水道・光熱費、保険料など必ず収入から差し引かれる費用のことを指します。これらは自分で金額の調整をすることは難しいので、毎月いくらかかっているのか必ず把握しましょう。
(3)貯金・投資したい金額を決める
もし将来のために貯金を考えているのなら、毎月(毎年)いくら貯めたいのかを検討します。金額を決めたら「収入(1)ー固定費(2)ー貯金したい額(3)=○○円(残金)」を算出しましょう。
この残った金額で予算を立てていきます。
(4)変動費を見積もる
変動費とは食費、交通費、交際費、趣味・娯楽費など、月々で金額が変動しやすい支出のことを指します。
ここで「2」で行った「消費・浪費・投資」の分類分けを生かします。
例えば「きれいになるために高額な美容費をかけたが、そこまで効果は感じなかったので少し削ろう」と思ったら趣味・娯楽費にかける予算を少し下げ、代わりに「体の内側からきれいにするための」食費の予算を上げる、など調整をします。
特に「消費と浪費」は意味の違いをしっかりと押さえながら予算を立てるのがポイントです。
②「本当に必要?」と購入前に自問自答をする
「あ、これいいな。欲しい!」と思ったら自分の心にこう聞いてみてください。
『それ本当に使う?』
『家にあるもので代用できない?』
『絶対に今必要なもの?』
たった一言、上記のような言葉を自分にかけてあげるだけでも、購入のハードルが上がります。
本当に節約をしたいのなら、買うより買わないことが一番の節約になるのです。
必要かどうか聞いてみたけどやっぱり欲しいと思ったものは、自分の幸福度を高めてくれる本物だということ。
衝動買いをしたときよりもよく考えてから手に入れたときの感動は、ひとしおですよ。
③使わなかった分でご褒美を
節約、節約…ばかりでは楽しくなくなってしまいます。
そもそもお金は浪費をするためにあるのですから、たまには使わないと節約は長く続きません。
そんなときこそ予算を立てて余ったお金で、自分にご褒美をあげましょう。
美味しい物を買って食べたり、旅行でちょっとしたいい所に泊まってみたり、節約として我慢していた美容にお金をかけてみたり…。
ポイントは「節約を頑張ってよかった!」と思えて、次の節約へのモチベーションを維持することに繋がるものに使うことです。
我慢をした先にご褒美があるので、次の節約も頑張れます。
6.まとめ
お金を使い過ぎてしまったときに、次に生かす方法をご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?
お金を使い過ぎないようにするコツは「消費・浪費・投資」の意味の違いをしっかりわきまえていること。
浪費を減らし、投資に回す金額を増やすことで、充実した生活や安心した将来を得ることができます。
筆者は、『投資だと思っていたものが実は浪費だった』と気づけたなら、その経験自体が次に繋がる大切な『投資』になると考えています。
失敗や後悔を上手に生かして、今より豊かな生活を送っていきましょう。